「FP&Aはつらい」「やめとけ」「つまらない」——そんな声を耳にしたことはありませんか?
本当はめっちゃくちゃ面白い職種なんです。
確かに、経営陣と現場の板挟みになったり、数字の計算ばかりに追われたりと、苦労が多い仕事であることは事実です。事業への直接的な貢献を感じにくく、やりがいを見失ってしまう人も少なくありません。
しかし、実際に経験してみると見えてくるのはまったく別の景色です。FP&Aは、数字を通じて会社の未来を描き、経営と現場をつなぐ“参謀”として機能する存在です。経営層に近い立場で意思決定に関わり、事業を成長させる仕組みを支える醍醐味は、他の職種では得がたいものです。

FP&Aはファイナンスキャリアの花形やで
本記事では、なぜFP&Aが「つらい」と言われるのか、その理由を整理した上で、実際にはどれほど重要でやりがいの大きいキャリアであるかを解説していきます。
FP&Aはなぜ「つらい・やめとけ」と言われるのか?
- 経営陣と現場の板挟みになり、調整役として精神的に疲弊しやすい
- 数字の集計や予実差異分析など計算作業が多く、ルーチンに感じやすい
- 事業への直接的な貢献を実感しにくいため、やりがいを見失う人もいる
FP&A(Financial Planning & Analysis)は、企業の成長を数字の面から支える重要な役割です。しかし、実際に働く人の声を聞くと「しんどい」「やめとけ」といった意見も少なくありません。その背景には、経営と現場の間に立つ特有のストレスや、定型的な数値管理に追われる日常が影響しています。
もちろんFP&Aは将来性が高く、経営に直結するやりがいのある仕事でもありますが、なぜ一部の人には「つらい」と映るのかを理解することは、キャリア選択において非常に大切です。
経営陣と現場の板挟みになるストレス
FP&Aの代表的な悩みは、経営陣と現場の双方から求められる要求に応える“板挟み”の立場にあることです。経営側は「売上・利益目標を達成できるのか」という厳しい視点を持ち、現場側は「リソース不足や予算制約でこれ以上は難しい」と現実的な声を上げます。FP&Aはこの両者をつなぎ、折り合いをつける役割を担うため、どうしても緊張感のある場面が多くなります。
特に月次・四半期決算のタイミングでは、現場に追加データや修正を依頼しつつ、経営には迅速なレポート提出を迫られる状況が頻発します。こうした状況が続くと、「誰からも感謝されず、ただ数字を合わせるだけの仕事」と感じてしまう人もいます。実際には調整力こそがFP&Aの核心スキルなのですが、ストレスフルな側面として語られることが多いのです。
単なる作業者に感じやすい日常業務
FP&Aが「つまらない」と言われるもう一つの理由は、数字を扱う作業の繰り返しに見えることです。予算策定、予実差異分析、レポート作成といったタスクは確かに欠かせない一方で、慣れてしまえば毎月同じ流れに思えてしまいます。
また、他部署からすると「数字をチェックしているだけの部門」と見られることもあり、事業に直接インパクトを与えている実感を得にくい点もあります。特に若手のうちは経営会議に出席する機会も少なく、「事業の舵取りに関われていない」と感じてしまうのです。
とはいえ、これらの分析や数値管理は経営判断の基盤そのものであり、裏方に見えても会社を支える重要な役割を果たしています。単なるルーチンにとどまるか、戦略的な分析へと発展させられるかは、本人の取り組み姿勢と環境次第ともいえるでしょう。
経営陣と現場の板挟みになるストレス
- 経営陣の高い要求と現場の制約の間で調整役を担うため、精神的負荷が大きい
- 予算編成では収益性と成長性の間で難しい配分判断を迫られる
- 予測と実績の乖離が生じるたびに原因を分析し、双方に納得感のある説明が必要
FP&Aに携わる人が「つらい」と感じる最大の理由は、経営陣と現場の双方の視点を調整しなければならない立場にあることです。経営は「利益最大化」「成長戦略の推進」といった大局的な視点で物事を判断しますが、現場は「人員不足」「顧客対応」「短期的なコスト圧力」といった現実的な制約の中で動いています。
この両者の間で数字を取りまとめ、説得力のある計画やレポートを仕上げるのがFP&Aの役割ですが、それは時に板挟みとなり、大きなストレス要因となるのです。
経営陣と現場の“温度差”を埋める調整役
FP&Aは経営陣と現場の“温度差”を埋める存在です。経営陣からは「来期は前年比二桁成長を実現したい」といった強気の要求が出される一方、現場からは「現状のリソースでは維持すら難しい」と悲鳴に近い声が上がります。この乖離を無視して一方に寄せれば、もう一方の不満を招き、組織全体の信頼を損なうことになります。
特に大変なのは、FP&A自身がどちらの立場にも完全には立てないという点です。経営陣に対しては現場の実情を理解した数字を提示しなければならず、現場に対しては経営の要求をかみ砕いて伝えなければならない。その過程で、どちらからも「都合の良い数字を作っているのでは」と誤解されることもあります。こうした“見えないプレッシャー”は、FP&A独特のストレス要因です。
予算編成における配分の難しさ(経験談)
実際にFP&Aを担当していて一番しんどいと感じるのが、限られた予算をどう配分するかという局面です。数字の計算だけなら機械的にこなせますが、問題は「どの部門にどれだけ配分するか」の判断です。
私が経験したケースでは、利益を安定的に稼いでいる既存事業と、まだ赤字だけれど経営が「将来の柱に育てたい」と考えている新規事業がありました。経営陣は「成長投資を優先したい」と言う一方、現場は「今の体制では目標を達成するのも厳しいから、まずは人員増強が必要だ」と訴えてきます。
どちらの言い分も正しいので、FP&Aとしてはどちらかを切り捨てるわけにもいかず、経営と現場の双方が納得する落としどころを探ることになります。



経営と現場どっちの味方にもならないといけないし、
本当に重心の置き方がむずいとこ
会議の場では「この配分が本当に合理的なのか」と経営から突っ込まれ、現場からは「結局いつも数字合わせで現実を見ていない」と批判される。まさに板挟みの瞬間で、精神的な負荷はかなり大きいです。
予測と実績の乖離に対する説明責任(経験談)
もう一つ、FP&Aで避けて通れないのが、予測と実績が大きく乖離したときの説明責任です。
例えば、私が関わった案件では、市場の急変によって売上が予測を大きく下回ったことがありました。原因は一部の大型顧客の解約だったのですが、経営会議では「なぜ事前に察知できなかったのか」「次回はどう防ぐのか」と矢継ぎ早に質問が飛んできます。数字のロジックだけで答えるのではなく、現場の事情も踏まえて説明しなければならないのが大変です。
一方で現場からは「計画自体が高すぎる」「もっと柔軟に見積もってほしい」と不満が出ます。FP&Aとしては、経営には冷静な分析を、現場には納得感のあるフィードバックを示さなければなりません。どちらかに偏ると「経営寄り」「現場寄り」とレッテルを貼られ、信頼を失いかねないのです。
正直、こうした乖離対応の場面では「自分のせいじゃないのに責任を問われている」ような感覚に陥ります。ただ、その局面を乗り越え、原因を整理して次の改善策まで落とし込めたときに、初めてFP&Aとしての存在意義を実感できるのも事実です。
数字の計算ばかりで“作業者”に感じてしまう瞬間
- 予実差異分析やレポート作成など、定型業務の繰り返しで単調に感じやすい
- 経営会議での発言権が少ないと「計算するだけの人」と見られやすい
- 戦略や意思決定に関与できない状況では、モチベーションが下がる
FP&Aは本来、経営の意思決定を支える参謀機能を果たすべき存在です。ところが実際の現場では、数字の集計やレポート作成に追われ、単なる“計算係”として扱われてしまう瞬間が少なくありません。こうした状況が続くと「自分は作業者に過ぎないのでは」と感じ、やりがいを失う要因になります。
もちろん数字を正確に扱うことはFP&Aの根幹ですが、そこに戦略的な視点や提案の余地がないと、キャリアとしての価値を実感しにくくなってしまうのです。
繰り返しの分析業務に追われる日常
FP&Aの代表的な業務に、予算と実績の差異分析や月次レポートの作成があります。これらは経営に必要不可欠なプロセスであるものの、内容は毎月似通っており、慣れてしまうとルーチンワークに感じてしまいます。
例えば「売上が計画を下回った」「コストが想定以上にかかった」といった差異を数字で整理し、原因を箇条書きにしてまとめる作業は、重要である反面、数字を並べ替えるだけの作業に見えてしまうことがあります。特に若手のうちは、分析結果を報告しても経営陣の議論にほとんど関われず、上司から「次回までにデータを直して」と指示を受けるだけに終わることも少なくありません。
こうした繰り返しが続くと、「戦略に貢献している感覚がない」「自分は表計算ソフトを操作する人にすぎない」と感じやすくなります。これはFP&Aとして成長したい人にとって、大きなフラストレーションとなります。



大事なのは、
作業自体は退屈かもやけど、分析業務自体はめっちゃ重要
徹底的に自分のものにすべき
経営会議で“数字要員”として扱われるもどかしさ
もう一つ、FP&Aが“作業者”に感じやすい瞬間は、経営会議や部門会議での立ち位置です。会議に同席していても、発言を求められるのは「売上の最新数字はいくらか」「今月の差異はどの程度か」といった事実確認に限られるケースが多いのです。
その場では、あくまで経営陣の意思決定を補助する「データ提供者」という役割にとどまり、戦略的な提案や意思決定への関与が許されないことがあります。実際に私が経験した場面でも、詳細な分析を行って改善提案まで用意したのに、会議中は「数字の訂正」しか求められず、虚しさを覚えたことがあります。
こうした状況が続くと「FP&Aは結局、経営が使いやすいように数字を整えるだけの部門だ」と捉えられてしまい、本人もモチベーションを失いやすいのです。もちろん、本来のFP&Aは数字を材料にして議論を深める役割を持つべきですが、その機会が与えられない環境では、“作業者扱い”から抜け出すのは難しいと感じるでしょう。
事業貢献の実感が得にくいと言われる理由
- FP&Aは成果が間接的であり、自ら売上や利益を直接生み出すわけではない
- 提案が経営判断に反映されても、成果への寄与度が見えにくい
- 現場や顧客と距離があるため、手応えを感じにくい瞬間がある
FP&Aは企業にとって欠かせない存在ですが、実際に働いていると「自分の仕事がどの程度会社に貢献しているのか分からない」と感じることがあります。なぜなら、成果が直接的ではなく、間接的に表れる性質が強いからです。営業職のように売上数字に直結するわけでも、開発職のように製品を世に送り出すわけでもありません。
そのため「自分の努力がどのくらい成果に結びついたのか」を測りにくく、やりがいを実感しにくいのです。
成果が「間接的」だから感じるもどかしさ(経験談)
私自身、FP&Aとして分析や予算策定に関わっていた頃、成果が間接的であることのもどかしさを何度も感じました。例えば新規事業への投資判断をサポートする資料を作成し、経営会議で提案が採用されたことがあります。その後、実際に事業が成長し、売上も拡大していきました。
しかしそのとき、正直「自分の分析がどの程度寄与したのか」が分かりませんでした。経営陣の決断、現場の努力、そして市場環境の追い風——それらが複雑に絡み合って成果につながったのであり、私の関与はその一部に過ぎないのです。結果として数字が伸びても、「本当に自分が役に立ったのか」という確信は得られませんでした。
このようにFP&Aは、成果を“自分の手柄”として実感しにくい構造を持っています。間接的な役割であるがゆえに、成功の手応えが薄く感じられるのです。
現場や顧客との距離から生まれる手応えの薄さ(経験談)
さらにFP&Aは、現場や顧客との距離も感じやすいポジションです。日々の業務は数字の分析やレポート作成が中心で、顧客と直接やり取りすることはほとんどありません。営業や開発のように「顧客の反応をその場で感じる」という瞬間が少ないため、どうしても間接的な仕事に見えてしまいます。
私が担当したとある予算策定では、営業部門と議論を重ねながら数値を組み立てました。最終的に計画は承認され、営業活動もスムーズに進んでいったのですが、売上が伸びた際に「これは営業が頑張った結果だ」と評価されることはあっても、「FP&Aが支えたからだ」と表立って言われることはありません。裏方の役割であるがゆえに、評価が伝わりにくいのです。



やっぱり、
自分でプロダクトをつくる、
自分で顧客獲得する、
ていう方が社会での成果は目に見えるよね
このような経験を重ねると、「自分は本当に事業に貢献できているのだろうか」と疑問を持つ人が出てきます。もちろん、FP&Aがなければ正確な予算管理や投資判断はできないのですが、成果が表に見えにくいことが、仕事を「つらい」と感じさせる理由の一つになっているのです。
本当は企業に不可欠なFP&Aという存在
- FP&Aは経営の意思決定を数字で支える参謀的役割を担っている
- 資金配分や投資判断に不可欠で、企業成長の基盤を作る存在
- 単なる数字の管理ではなく、未来を描く戦略的ファンクション
「つらい」「作業者に見える」と言われることもあるFP&Aですが、実際には企業の経営に欠かせない不可欠な存在です。なぜなら、彼らの分析や提案がなければ、経営陣は確かな根拠を持って意思決定することができないからです。営業や開発が成果を生み出すためにも、FP&Aが舞台裏で数字を整え、方向性を示すことが前提となっています。
経営の意思決定を支える“参謀”としての役割
FP&Aの真価は、数字を通じて経営の意思決定を支える参謀的機能にあります。単に「予算と実績の差異を報告する」だけではなく、その背景にある事業の動きや市場の変化を読み解き、今後のアクションにつなげる提言を行うことが期待されます。
例えば、新規事業への投資判断の場面では、将来キャッシュフローのシナリオを複数提示し、リスクとリターンを見極める材料を提供します。経営陣はその分析を踏まえて意思決定を行い、現場はその方針の下で行動します。つまり、FP&Aが提示する分析の質次第で、会社の戦略全体が大きく変わり得るのです。



ここの意識がめっちゃ重要
目線を高く持ってその”参謀”としての役割をこなせるかどうかが分かれ道
私自身も過去に、経営陣が「事業を縮小すべきか拡大すべきか」で迷っていた際、シナリオ別の損益予測を提示し、結果的に撤退判断を後押しした経験があります。直接売上をつくったわけではありませんが、数字をもとに正しい方向性を示すことができたと実感した瞬間でした。
成長の基盤をつくる“戦略的ファンクション”
FP&Aは「数字を管理する部門」と思われがちですが、実際には未来を描く戦略的ファンクションです。資金配分や投資計画を通じて、どの事業に注力し、どの領域を縮小すべきかを示す。その判断は、企業が限られたリソースをどこに投じるかを決める極めて重要なプロセスです。
また、FP&Aは経営陣と現場の橋渡し役でもあります。現場の数字を吸い上げ、それを経営が意思決定に使える形に翻訳する。逆に、経営の方針を現場に落とし込み、数字を伴った計画として浸透させる。この双方向のコミュニケーションがあるからこそ、組織は一枚岩となって戦略を遂行できます。
経験上、特に中期経営計画やM&Aの検討などではFP&Aの関与が不可欠です。経営が掲げる成長ストーリーに現実味を持たせ、実行可能な数値計画に落とし込むのはFP&Aの役割だからです。企業の成長の土台を形づくる“見えない力”こそFP&Aだと言えるでしょう。
経営と現場をつなぐ役割
- FP&Aは経営戦略を数字に翻訳し、現場に落とし込む橋渡し役
- 現場の声や実情を吸い上げ、経営判断に反映させる調整力が不可欠
- 数字だけでなく、ストーリーを描き、組織全体を動かす“参謀機能”を担う
FP&Aの最大の価値は、経営と現場をつなぐ参謀として機能することにあります。経営は大局的な戦略を描き、現場は日々の業務を回す。両者の間にはどうしても温度差や認識のギャップが生まれます。その橋渡しをするのがFP&Aであり、単なる数字の管理者ではなく、戦略実行を支えるキーパーソンとして存在しているのです。
経営の戦略を“数字”に翻訳して現場へ
経営陣が描くビジョンや中期戦略は、多くの場合「市場シェアを拡大する」「新規事業を成長させる」といった抽象度の高いものです。しかし現場にとっては「そのためにどの程度の売上目標を追うのか」「どんなコスト構造に抑えるべきか」といった具体的な数値が必要です。
FP&Aはここで、経営の言葉を数字に翻訳し、現場が行動できる計画に落とし込む役割を担います。予算策定やKPI設定を通じて「今年はこの商品で売上を何%伸ばす」「人員はどの部門に重点配分する」といった明確な指標を提示するのです。
私自身の経験でも、経営が掲げた「利益率改善」の方針を、各部門に具体的なコスト削減目標として示したことがありました。現場からは「ただ数字を押し付けられているのでは」と反発もありましたが、背景となる戦略意図を丁寧に説明することで、納得感を得ることができました。経営のビジョンを“数字を通じて理解可能な形”に変換することが、FP&Aの参謀機能の第一歩なのです。



やっぱりね、
原点として「数字」に徹底的に拘る、
この基本は絶対に守るべき
現場のリアルを経営判断に反映させる
一方でFP&Aは、現場のリアルな状況を経営に届ける翻訳者でもあります。現場は常に顧客対応やオペレーションの課題に直面しており、時には経営の描く計画との乖離が生まれます。FP&Aは各部門との密なコミュニケーションを通じて、その実態を数字として吸い上げ、経営陣に提示するのです。
例えば、営業現場が「人員不足で新規案件を追えない」と訴えている場合、それを単なる愚痴ではなく「人員一人当たり売上高の推移」「採算性のシミュレーション」といった形にまとめて経営に報告します。経営陣はそれを見て初めて、追加採用や重点投資の判断ができるわけです。つまりFP&Aは、現場の声をエビデンス付きで経営に届ける調整役として不可欠なのです。
経験上、ここで重要なのは「経営に都合のよい数字だけを出すのではなく、現場の実情を正しく反映させる」ことです。そうでなければ、机上の空論に基づいた戦略が進んでしまい、組織全体が疲弊します。FP&Aは数字を通じて両者の信頼関係を築き、経営判断を現実的なものにする役割を担っているのです。
本当に心構えとして大切なのは、板挟みになること自体がしんどいのは事実ですが、むしろその“板挟みの場”に立てるからこそ、FP&Aは経営と現場の両方に影響を与えられる。そこにこそ、この職種の本当の価値があります。
FP&Aがキャリアとして大きな価値を持つ理由
- 経営に最も近い立場で意思決定に関与できるため、視座が高まる
- 財務・会計・戦略の知識を横断的に習得できるため市場価値が高い
- 転職・キャリア展開に強く、CFOや経営企画へのステップアップにつながる
FP&Aは一見すると地味に映るかもしれませんが、実はキャリアとして極めて価値の高いポジションです。経営と現場の間で数字を扱うだけでなく、企業の意思決定の根拠を作り出す存在であり、その経験は将来のキャリアに直結します。特に20〜30代のうちにFP&Aを経験しておくと、「数字で経営を語れる人材」として市場価値が大きく高まるのです。
経営に近い立場で“視座”を鍛えられる
FP&Aの最大の魅力は、経営に直結する立場で仕事ができる点にあります。予算策定、投資判断、業績予測といった業務はすべて経営陣の意思決定とつながっており、日常的に経営層とやり取りする機会が多いのが特徴です。
私自身、FP&Aとして働いていたときに感じたのは、数字を通じて会社全体を俯瞰できるという点です。営業や開発といった一部門に閉じず、事業全体の成長戦略をどう設計するかを常に意識する必要があります。そのため、「自分の部署」ではなく「会社全体」の視点で物事を考える力が自然と身につきます。
この“視座の高さ”は、後々経営企画やCFOといったポジションを目指す上で欠かせない資質です。若いうちからFP&Aを経験することで、他の職種では得られにくい経営感覚を磨くことができるのです。
市場価値の高いスキルセットが身につく
FP&Aで培われるスキルは、財務・会計・戦略の知識を横断的に活用できる点にあります。単に数字をまとめるだけでなく、予算の背景を理解し、事業のリスクを見極め、将来のシナリオを設計する能力が求められます。
この経験は、転職市場において非常に高く評価されます。外資系企業やコンサルティングファーム、さらには事業会社の経営企画ポジションでも、「数字をもとに戦略を語れる人材」は常に不足しているからです。実際、FP&Aを経てCFOや事業責任者にキャリアアップした事例は数多く存在します。
私自身も転職活動の際、FP&Aの経験を評価され、「単なる経理ではなく、経営に近いポジションを担ってきた」という点で大きなアドバンテージを感じました。数字を扱いながら経営を動かす経験は、どの業界・職種においても通用する強力な武器となります。
つらいどころか面白い!私が実際に経験したFP&Aで得られる成長とやりがい
- 事業を成長させる“数字の武器”として課題を可視化できる
- 経営層の意思決定に関わり、組織を動かす醍醐味がある
- 専門性が高く、他社でも通用するフレームワークを習得できる
- 財務会計とは異なる、未来志向の分析と提案が中心
「FP&Aはつらい」「やめとけ」と言われることもありますが、実際に経験してみるとその印象は大きく変わります。FP&Aは確かに地道な分析や調整も多い仕事ですが、事業の成長を数字で後押しし、経営を動かす面白さを味わえるポジションです。単なる作業者ではなく、参謀として会社の未来を形作る役割を担える——その成長実感は他の職種では得がたいものがあります。
事業を成長させる“数字の武器”を手にできる
実際に私が経験して強く感じたのは、FP&Aの面白さは「数字で課題を明らかにし、事業をグロースさせる力」にあるということです。財務会計が過去の取引を正しく記録するのに対し、FP&Aは未来を見据えて「どこに投資するか」「どこを改善するか」を数字で示す役割を担います。
例えば、ある新規事業で思うように利益が出なかった際、売上構造やコスト配分を詳細に分析することで、マーケティング費用の配分に問題があることを突き止めました。その改善提案を実行した結果、事業は黒字転換に成功。営業や開発が必死に努力していた課題を、数字というレンズで“見えなかった原因”を可視化できたことに大きなやりがいを感じました。
FP&Aは「数字を扱う裏方」ではなく、数字を武器にして事業を前進させる存在です。その瞬間に立ち会えることこそ、この仕事の醍醐味だと思います。
経営層に近い立場で意思決定に関われる
もう一つの大きなやりがいは、経営層に近いところで意思決定に関わることができる点です。日々の分析やシナリオ作成が、そのまま経営会議の議題に上がり、戦略判断の土台となります。
私自身、経営陣が新規プロジェクトへの投資を検討していた際、複数の収益シナリオを作成しました。その結果、「短期利益は薄いが、中長期では確実に市場シェア拡大につながる」という見解を示し、最終的に投資決定がなされました。自分の作った資料や分析が、会社全体の進路を左右する判断に直結するのを目の当たりにしたときの高揚感は、他では得られないものです。
経営会議に同席し、経営陣が議論する姿を間近で見られるだけでも学びは多く、自然と視座が高まります。「経営の言葉を理解し、自分の数字で貢献する」——その実感がFP&Aの大きな魅力です。
専門性がキャリアの強みになる
さらにFP&Aの仕事は、専門性が高く、他社でも通用するフレームワークを習得できるという点でも価値があります。予算策定、予実差異分析、シナリオプランニングといったスキルは、どの業界・企業でも共通して求められるものです。
私自身、転職活動で「FP&A経験者」という肩書きが大きな武器になったことがあります。特に外資系やコンサル、事業会社の経営企画などでは、「数字を使って経営に貢献できる人材」は常に不足しており、即戦力として評価されやすいのです。
また、FP&Aは単なる分析者にとどまらず、経営と現場をつなぐコミュニケーション能力も磨かれます。数字に基づいてロジカルに説明しつつ、現場の納得感を得られるように調整する。こうした経験を積むことで、どの職場に移っても活躍できる“汎用性のある専門性”を身につけられるのです。
まとめ
FP&Aは「板挟みがつらい」「数字ばかりで作業者に見える」「事業貢献の実感が薄い」といったネガティブな声を集めやすい職種です。しかし、その実態はむしろ逆であり、経営と現場をつなぐ参謀として企業に不可欠な存在です。
数字を通じて経営判断を支え、課題を可視化し、事業を成長させる力はFP&Aならではの価値です。経営層に近い立場で意思決定に関われる経験は視座を高め、財務・戦略・事業理解を横断的に身につけることができます。これはどの業界でも通用する専門性であり、キャリアの選択肢を大きく広げる財産となります。
「つらい」と言われるポイントは、裏を返せばFP&Aの存在意義そのもの。板挟みになるからこそ企業全体を動かす役割を果たせるし、成果が間接的だからこそ組織全体の成功を支える基盤となれるのです。FP&Aは決して“やめとけ”ではなく、成長とやりがいを実感できるキャリアの選択肢といえるでしょう。
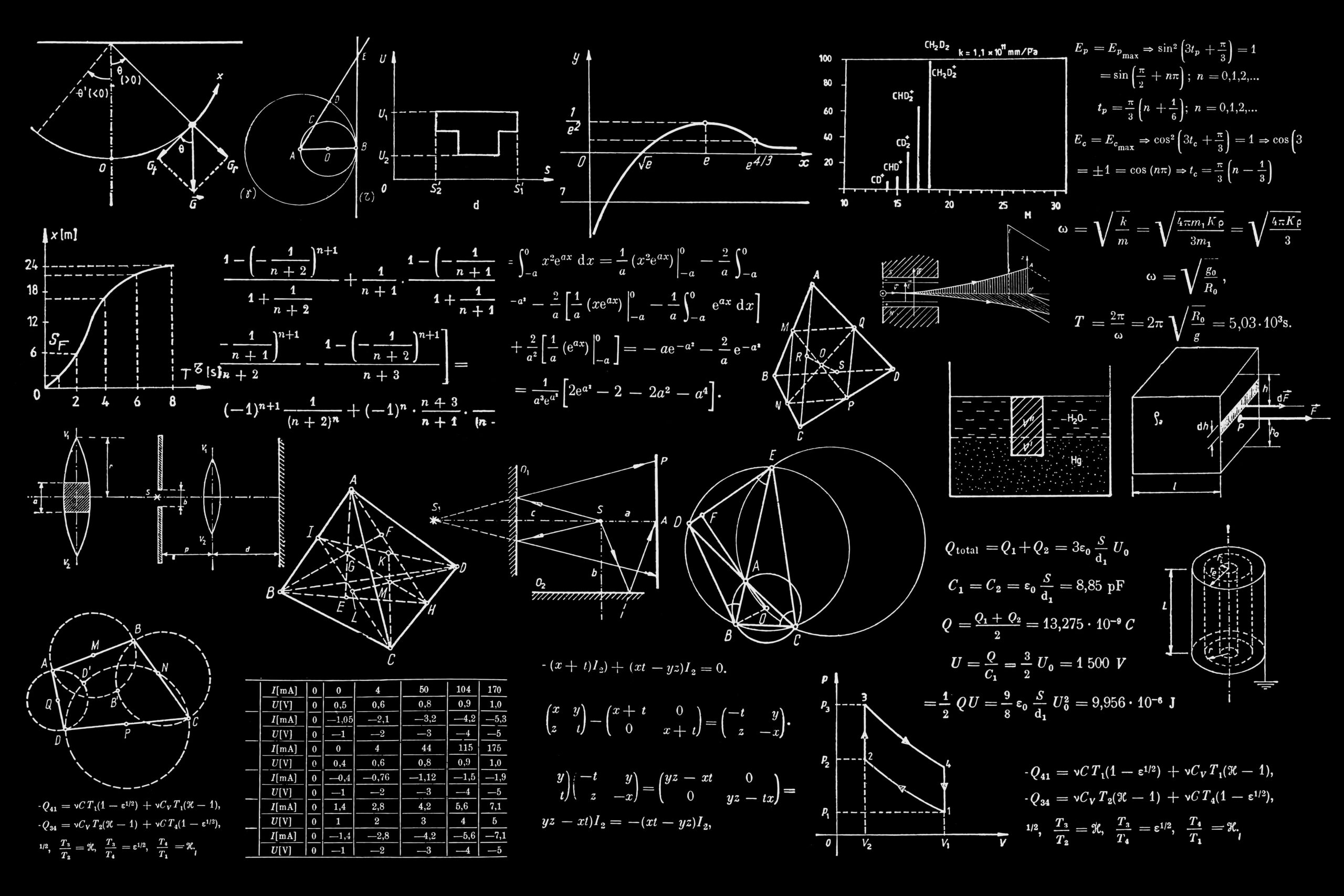








コメント