「30代前半で経理に転職したいけれど、もう未経験では厳しいのでは?」
そう不安に感じている方は少なくありません。20代であれば「若さ」や「ポテンシャル」で採用されることも多いですが、30代前半では状況が一変します。企業が求めるのは、“入社後にどう活躍できるか”を具体的に描ける人材です。

だからこそ、
30代前半になると自身のキャリア・転職活動に対して戦略を持ってるかどうかで大きく変わるんやで
実は、経理に全くかすっていないキャリアはほとんど存在しません。営業での数字管理や人事での給与計算など、あなたの経験の中には必ず「経理とつながる部分」があります。重要なのは、その経験をどう棚卸しし、“経理の言葉”に翻訳して伝えられるかです。
本記事では、30代前半の未経験者が経理転職を成功させるために必要な「即戦力思考」と、実体験から学んだ具体的な戦略を解説します。未経験でも正しく準備をすれば、経理キャリアの扉は確実に開けます。
30代前半の経理転職は「戦略」が必須
- 20代はポテンシャル採用が多いが、30代前半は「活躍イメージ」を具体的に示す必要がある
- 未経験でも「即戦力に近づく努力」を伝えることが重要
- 自己分析・経験棚卸し・学習実績を組み合わせて戦略的にアピールする
20代のうちは「若さ」や「ポテンシャル」が評価され、未経験でも採用されやすいのが現実です。しかし30代前半となると状況は一変します。
採用側は「この人が入社後すぐにどんな成果を出せるか」をシビアに見ています。未経験であっても“即戦力に近い形”で自分をアピールできなければ、選考を突破するのは難しいのです。ここでは、30代前半が経理に転職する際に必要となる「戦略的なアプローチ」について解説します。
20代と30代前半で評価基準はどう変わるのか
20代の転職は、将来性や柔軟さ、吸収力といったポテンシャルに重きが置かれます。たとえ業務経験が乏しくても、学習意欲やコミュニケーション力を示せば、十分にチャンスはあります。
一方で30代前半になると、採用担当者の視点は「即戦力寄り」に移ります。具体的には「これまでの経験を経理業務にどう応用できるか」「入社後すぐに戦力化できるか」が問われます。そのため、ただ「経理に挑戦したい」という熱意を伝えるだけでは不十分で、「私はこういう形で経理に貢献できます」と明確に伝えられることが不可欠です。
未経験でも“即戦力に近づく努力”をどう示すか
30代前半から経理を目指すなら、「経験の棚卸し」と「学習の積み重ね」が必須です。まず、これまでの仕事の中に経理に直結するスキルを見出しましょう。営業での売上管理や予算調整、事務職での請求書処理や経費精算、人事での給与計算などは、すべて経理業務と親和性が高い経験です。
次に、知識面での裏付けを示すために簿記資格の取得を進めます。特に簿記2級は「基礎を理解している証明」として強力に作用します。資格は単なる飾りではなく「学ぶ姿勢」「数字に強い基盤」を示すための具体的な証拠になります。
さらに、“成長の余地”をポジティブに見せることも大切です。「即戦力とは言えないが、2〜3か月で基本業務をキャッチアップし、その後は業務改善に貢献できる」といった現実的な成長プランを提示できれば、面接官の信頼を得やすくなります。
未経験から経理を目指す一番の有効策は「簿記2級」取得
- 簿記2級は「最低限の会計知識」を証明する資格として、経理転職で必須に近い位置づけ
- 学習時間は300〜500時間程度が目安で、30代社会人でも十分に現実的
- 簿記1級は高度であり、一般企業の経理担当にはオーバースペックになることが多い
経理に未経験で挑戦する場合、「知識の裏付けをどう示すか」は避けて通れない課題です。
特に30代前半では「やる気」や「ポテンシャル」だけでは採用されにくく、客観的なスキル証明が欠かせません。その中で最も有効な手段が、日商簿記2級の取得です。経理の基礎を体系的に学べるだけでなく、面接で”本当に経理業務に興味がある”と伝える武器にもなります。



必要なのは数ヶ月の時間とわずかな費用、
それで実務に直結する資格やから取らない理由が無いんよ
なぜ簿記2級が「最低限必要」とされるのか
企業の採用担当者は、経理未経験者を採用する際に「本当に業務を理解できるのか」を不安視します。その不安を払拭する最もわかりやすい手段が簿記2級です。
簿記3級は商業簿記の基礎にとどまり、伝票起票や仕訳の初歩レベルが中心です。確かに入門としては有効ですが、実際の経理業務では「仕訳を覚える」だけでなく実務に直結する知識が求められます。採用側も「2級を持っていれば一通り理解しているだろう」と判断しやすいのです。
特に30代前半の転職では「未経験だけど即キャッチアップできる」という安心感が重視されます。その意味で、簿記2級は経理職へのエントリーチケットのような存在と言えます。
学習時間と難易度|30代社会人に現実的か?
簿記2級の合格に必要な学習時間は、多く見積もっても300〜500時間とされています。フルタイム勤務の社会人が平日に1〜2時間、休日に3〜5時間学習するペースでも、4〜6か月で十分に到達可能です。
「簡単に取れる資格」と表現されることもありますが、実際は真剣に学ばないと合格できません。特に工業簿記や連結会計といった論点は、初学者にとって難所になりがちです。
また、近年はオンライン講座やアプリなど、学習環境が格段に整っています。通勤時間やスキマ時間を活用すれば、十分に現実的な学習計画を立てることが可能です。忙しい30代でも「半年で合格」は十分に実現できる範囲です。
簿記1級の位置づけ|狙うべき人と狙わなくて良い人
ここで気になるのが「どうせなら簿記1級まで取った方が良いのでは?」という疑問です。ただ、”未経験でこれから経理を始める”という文脈では簿記1級はオーバースペックであると考えています。
簿記1級は難易度が一気に上がり、学習時間は1,000時間以上が目安とされます。合格率も10%前後と低く、実務経験がない状態で挑戦するにはかなりの覚悟が必要です。もちろんさくっと取れるほどのそもそもの学力があれば良いですが、基本的にその学習時間を投下する前に先に転職して経理実務に携わった方が良いです。
簿記1級は、会計士や税理士といった専門職を目指す場合や、上場企業で財務経理を担当する場合に強力なアピール材料となります。しかし、一般企業の経理担当として未経験から入る段階では「オーバースペック」と見られるケースも少なくありません。むしろ「資格ばかりで実務がない」と逆に懸念される可能性すらあります。
したがって、未経験からの第一歩としては簿記2級で十分です。そこから経理に転職し、実務経験を積んだ上で「より高みを目指したい」と思った時に簿記1級や会計士などへステップアップするのが現実的なキャリアパスと言えるでしょう。



もちろん1級があれば評価もかなり変わる、
ただ、取得に必要な時間を考えると、30代前半であればまず転職した方が良いかと
実際の採用場面での優先順位|資格よりも経験を重視
財務経理の世界では「資格を持っているか」より「現場での実務経験」が最も評価されます。例えば、私が以前見た採用現場ではこんなケースがありました。
- Aさん(37歳):簿記1級を保有。前職は営業職で、経理の実務経験はゼロ。
- Bさん(30歳):簿記2級を保有。中小企業でアシスタント的に請求書処理や経費精算を半年ほど経験。
どちらも「未経験枠」で応募しましたが、採用されたのはBさんでした。理由は明確で、すでに経理の仕事に触れており、入社後すぐに戦力化できる見込みがあるから、です。Aさんは資格の知識は豊富でも、現場経験がなく、即戦力イメージを描きづらいという判断でした。
採用担当者が重視するのは「決算を任せられるか」「入社後すぐに数字を正しく処理できるか」という実務力。会計の理論や資格知識はもちろん役に立ちますが、それだけでは不十分です。財務経理の業務は会社ごとの会計システムや内部ルールに依存する部分が大きく、資格<経験、理論<現場という現実があるのです。
だからこそ、資格の勉強に時間をかけすぎるよりも、できるだけ早く現場に入り、仕訳や決算に触れる方がキャリア形成には有利です。資格は「後から経験を整理して理論武装するための武器」と考えた方が実践的です。
実際の採用場面では、「簿記1級を持つ30代後半の未経験者」より「簿記2級を持っている20代で、請求書処理を経験した人」の方が優先される。この構図こそが、経理転職市場のリアルなのです。



経理って簿記等の資格がいっぱいあるから勘違いされがち、
30代以降は意外なほどに実務経験を重要視するで
未経験転職のハードルを下げる具体的方法
- 経理未経験でも、事務・営業・人事などの業務は経理と直結している
- 営業経験は「ミドルオフィス業務」として業績管理・調整力をアピール可能
- バックオフィスはシステムとの親和性が強く、ITスキルを示せば差別化できる
- 「完全未経験」という人はいない。自分の経験を“経理の言葉”に変換することが重要
「経理に転職したいけれど、自分は完全未経験だから不利だ」と思い込んでいませんか?実はその考え方自体が誤解です。事務で請求書を処理した経験、営業で売上や予算を管理した経験、人事で給与計算や社会保険料を扱った経験。これらはすべて経理業務と地続きであり、アピール次第で“実務に直結する強み”になります。
さらに営業経験者は「ミドルオフィス」的な役割を担うことで数字に強い人材として評価され、バックオフィス系の業務ではシステムとの親和性を示すことで市場価値を高められます。
重要なのは「自分の経験をどう経理の言葉に翻訳して伝えるか」。ここからは、具体的な経験をどうアピールに変換できるかを整理していきます。



まずは、
自身のキャリアを棚卸ししてアピール
さらには経理に近しい領域にシフトすることを検討
親和性のある経験を棚卸しする(「完全未経験」は存在しない)
経理は「バックオフィスの一部」として切り離されがちですが、実際には営業や制作といった事業部門から、総務・人事など他のコーポレート部門に至るまで、日常的に連携することの多い仕事です。売上・経費・給与・契約といった会社の数字は、すべて経理を通じて記録されるからです。
そのため、「経理実務にまったくかすっていない」という人の方がむしろ珍しいと言えます。請求書処理や経費精算、売上や予算管理、給与計算や社会保険対応など、ほとんどのビジネスパーソンがどこかで経理業務と接点を持っています。
大切なのは「自分の経験をどう棚卸し、経理の文脈で語り直すか」。経理の実務フローを大枠で理解したうえで、親和性のある経験を自信を持って伝えれば、未経験であっても「すでに経理の一端を担ってきた人材」として評価されるのです。
事務職の経験|請求書処理・経費精算
事務職で担当することの多い請求書処理や経費精算は、経理業務と直結しています。請求書の内容を確認し、社内承認フローに回す作業は「債務管理」や「買掛金処理」の一部に該当します。経費精算についても、領収書の突合や金額チェックは「旅費交通費」「福利厚生費」といった勘定科目にそのまま結びつきます。
このように説明すると、「私はすでに経理の基礎部分を経験していた」と胸を張れる領域であることが分かります。事務職の経験は単なる雑務ではなく、経理実務を支える重要な要素なのです。
営業職の経験|売上管理・予算管理
営業は「数字をつくる仕事」と思われがちですが、実際には「数字を管理する仕事」でもあります。毎月の売上を集計し、目標との乖離を把握したり、利益率を確認したりする作業は、まさに経理の「予算実績管理」と一致しています。
また、売上データや案件進捗をExcelで整理し、レポートを作成する経験は、経理における業績分析や管理会計レポートの基礎につながります。営業経験をそのまま語るのではなく、「数字を扱い、分析し、改善に役立てた」という経理的視点で言い換えることが大切です。
総務・人事の経験|給与計算や社会保険対応
給与計算や社会保険の業務は、人事・総務の担当範囲に思えますが、会計処理と密接に関わっています。給与明細に記載される金額は、経理側で「人件費」として処理され、源泉所得税や社会保険料は国や自治体への納付義務と直結しています。
そのため、給与計算を担当した経験は、「人件費や福利厚生費の仕訳に強い人材」として経理職に直結する強みです。さらに、給与計算ソフトや社会保険システムを扱った経験は、経理が使う会計システムやERPとも親和性が高く、システム理解力を示す材料になります。
営業経験を活かすなら「ミドルオフィス業務」にシフト
さらに、営業経験や事業部での経験を活かして「ミドルオフィス業務」にシフトすることで、経理業務にかなり近づきます。バックオフィスに完全に移らなくても、営業活動を支える「営業管理」や、契約・請求をめぐる経理や法務とのやり取りは必ず発生します。ここを意識的に担うことで、営業から経理へのブリッジを作ることができるのです。
営業管理や経営管理として業績管理に携わる
営業現場では、売上や受注件数を毎月集計し、目標との差を可視化する業務が欠かせません。これは単なる営業資料の作成ではなく、数字をもとに組織の意思決定を支える「管理会計的な業務」です。
たとえば、Excelで売上データをピボット化し、商品別・地域別の収益性を分析する。あるいは、部門ごとの利益率を算出して経営層にレポートする。これらは経理が日常的に行う「予算実績管理」や「業績分析」と同質のものです。
「営業で培った業績管理スキルは、経理の管理会計に直結する」と伝えるだけで、面接官に即戦力としてのイメージを持たせることができます。
経理や法務との橋渡し役を担う
営業活動を進める上で避けられないのが、契約条件の調整や請求・入金に関する確認です。ここで経理や法務とのやり取りを経験していることは、転職時に強力な武器になります。
例えば、顧客の要望に合わせて契約書の文言を調整する際に法務と協議した経験。請求金額や支払期日を巡って経理と調整し、スムーズに入金を進めた経験。これらは単なる補助的な仕事ではなく、事業部と管理部をつなぎ、リスクを回避しつつ数字を正しく扱うスキルの証拠です。
経理は部門横断的な調整力を強く求められる職種です。営業時代にこの橋渡し役を担った経験を語れる人は、未経験でも「経理的な素養がある」と高く評価されます。
業務改善を経験して“経理的視点”を磨く
営業部門では、数字の取り扱いに関する小さな非効率が大きなトラブルに発展することがあります。そのため、営業管理シートの改善や受発注フローの効率化を進めた経験は、そのまま「経理的思考」を身につけた証拠になります。
例えば、Excel集計が属人的で誤りが多かったために関数やマクロを活用して精度を高めた。案件の進捗管理が遅れていたため、営業・経理・システム部門と連携して管理プロセスを見直した。こうした取り組みは、「数字を正しく扱う仕組みを作る・改善する力」として経理に直結します。
経理は「仕訳入力担当」ではなく「業務フローの守護者」です。営業時代に改善意識を持って数字に向き合った経験を語れれば、即戦力に近い評価を得ることができます。
バックオフィス×システムの経験を積む、知見を貯める
経理業務はもはや「仕訳を打ち込むだけの仕事」ではありません。請求・入金・支払といった日々の処理をはじめ、決算や予算策定に至るまで、システム上でのデータ管理と切り離せなくなっています。
クラウド会計ソフト、ERP(基幹業務システム)、ワークフロー管理ツールなど、業務の基盤を支える仕組みを理解して運用できるかどうかが、経理の実力を大きく左右します。
そのため、バックオフィス業務とシステムの両面を経験し、知見を蓄積することは、経理転職において大きな差別化要因になります。未経験であっても、「数字」と「システム」の両方に触れてきた経験を語れる人材は、採用担当に安心感と期待感を与えるのです。
経理はシステムと切り離せない時代背景
経理業務は、請求書の受領・承認から支払処理、入金確認、売掛・買掛管理まで、すべてがシステムに依存しています。かつては紙ベースや手入力で行われていた処理も、今では電子帳簿保存法やインボイス制度の影響もあり、データ連携による自動化が急速に進んでいます。
その中で重要なのは「システムを理解できるかどうか」。操作に不慣れだと業務効率を落とすだけでなく、ミスや不正の温床にもなりかねません。逆に、**「システムを正しく理解して使いこなせる人材」**は、経理未経験でも高く評価されます。
ERP導入・システム開発経験は大きな強み
もしERP(SAP、Oracle、freeeなど)や基幹システムの導入プロジェクトに関わった経験があるなら、それは経理転職において圧倒的なアピールポイントです。
エンジニアとの要件定義や、現場業務をシステムに落とし込む調整役を務めた経験は、数字とシステムをつなげられる人材の証拠です。経理は日々の入力やチェックだけでなく、業務フローそのものを改善する役割も担うため、システム導入経験がある人は即戦力候補として扱われやすいのです。
特に30代前半の転職者にとっては「現場感覚+システム理解」を兼ね備えていることを示すことで、未経験のハンデを補って余りある評価につながります。
Excel・データ分析スキルをどう見せるか
経理業務におけるExcelスキルは、基礎ではなく「実践力」が問われます。表を整える程度ではなく、ピボットテーブルで集計し、VLOOKUPやINDEX/MATCH関数で効率的にデータを抽出し、場合によってはマクロを用いて業務を自動化できる人材が重宝されます。
さらに、営業成績や経費データを分析して改善提案に結びつけた経験があれば、数字を整理して活用する力として強くアピール可能です。30代前半の転職者にとっては、即業務改善に貢献できる人材という印象を与えるうえでExcel・分析スキルは欠かせない武器です。
ベンチャー企業・税理士事務所を経由して「経験者」になる
- 大手企業は経理未経験者の採用に消極的で「即戦力」を求めがち
- ベンチャーや中小企業では未経験でも採用されやすく、幅広い業務を経験できる
- 税理士事務所での会計実務経験は、一般企業経理に横展開できる強力なキャリア資産になる
30代前半から経理を目指す場合、大手企業にいきなり入るのは難易度が高いのが現実です。大企業では経理部門が細分化されており、採用では「即戦力」を重視する傾向が強いため、未経験者にチャンスは限られます。
そこで現実的かつ効果的な戦略が、ベンチャー企業や中小企業、あるいは税理士事務所を経由して「経験者」としてキャリアを積み、その後に大手企業や希望のポジションへ横展開していくルートです。
大手が厳しい理由と、ベンチャー・中小での成長機会
大手企業の経理部門は、すでに体制やルールが整っているため、採用では「すぐに決算を回せる」「特定領域に強い」といった即戦力を求められる傾向が顕著です。未経験者は「教育コストがかかる」「配置できる部署が限られる」と見なされ、書類選考で落とされやすいのが実情です。
一方でベンチャー企業や中小企業では、体制がまだ整っていないケースが多く、経理担当に幅広い業務を任せる傾向があります。仕訳・請求書処理から月次決算、資金繰り、場合によっては経営会議用の資料作成まで幅広く経験できます。「業務範囲が広い=経理として一気に成長できる環境」であり、未経験者にとって実務経験を積む絶好の場となります。
税理士事務所での会計実務は経理に直結する
税理士事務所に勤務する道も、経理未経験者には有効なキャリアの選択肢です。税理士事務所では、クライアント企業の仕訳入力から月次試算表作成、税務申告まで一連の会計業務に触れることができます。複数の会社を担当するケースも多いため、短期間で多様な業務に携われる点も強みです。
この経験は、そのまま一般企業の経理に横展開できます。実際に「税理士事務所で会計実務を経験 → 事業会社経理へ転職」というルートは非常に王道で、採用側からも「実務を理解している人材」として評価されます。未経験の30代が“経理経験者”に一気に変わる方法の一つが、税理士事務所でのキャリアなのです。
30代前半の経理転職で求められる心構えと面接対策
- 30代前半の経理転職では「ポテンシャル」より「即戦力に近い姿勢」が求められる
- 実務経験がなくても、業務改善や部門連携など攻めの姿勢を示すことが重要
- 面接では「どのように戦力化するか」を具体的に語れるかが合否を分ける
- 自分の過去経験を“経理的視点”に翻訳し、ストーリーとして語ることが成功のカギ
私もかつて経理実務の経験がないまま、経理に転職したことがあります。その際に意識したのは「資格」や「熱意」だけでなく、元いた会社の経理業務フローをできる限り理解し、面接で“即戦力イメージ”を具体的に伝えることでした。
20代であれば「若さ」や「ポテンシャル」で採用される可能性もあります。しかし30代前半になると、面接官が求めているのは「入社後、どのくらいで独り立ちできるのか」「業務改善や効率化にどう貢献できるのか」という実務寄りの視点です。したがって、面接対策の段階から「即戦力思考」を前面に出す必要があります。



「即」戦力じゃなくてもいいけど、
「すぐに戦力化」するイメージをどれだけ持ってもらえるか
面接で伝えるべき「即戦力思考」とは
経理未経験で挑戦する場合、もちろん最初から即戦力になるのは難しいでしょう。それでも面接官は「早期に戦力化できそうか」を見極めています。
よくあるんですが、経理職について「ルーティンだけをやりたい」という姿勢は絶対NGです。



これ本当にありがち
この生成AI時代にルーティン業務だけの人材は必要とされない
「最初は日次処理を着実に覚え、数か月で月次決算に関与し、改善提案もしていく」といった前向きな成長プランを語ることが有効です。「自分はこういうステップで戦力化する」という現実的なシナリオを提示できれば、未経験でも信頼感を与えられます。
さらに、Excelでのデータ集計やレポート改善の経験、業務フローを見直した経験、他部署との調整役を担った経験などを具体的に示すことで、面接官に「攻めの姿勢」を印象づけられます。
実体験から学んだ面接突破のポイント
私自身の面接でも、単に「頑張ります」と熱意を示すだけでは不十分でした。突破につながったのは、過去の経験を経理の言葉に置き換えたことです。
- 営業で培った業績管理 → 「予算実績管理」
- 契約や請求で経理・法務と調整した経験 → 「管理部門との橋渡し」
- Excelで部門レポートを改善 → 「数字を正しく扱う仕組みを作った」
こうした言い換えを面接で伝えた結果、「この人なら数か月後には戦力化できそうだ」と評価してもらえました。
結局のところ、面接で大切なのは「過去の経験を経理的に翻訳し、未来の活躍像を面接官にイメージさせること」です。未経験でもこの準備ができていれば、30代前半という年齢のハードルを越えて採用される可能性は十分にあります。
まとめ
30代前半からの経理転職は「未経験だから無理」と思い込む必要はありません。むしろ、これまでのキャリアをどう経理に結びつけ、即戦力として活躍できる未来像を描けるかが合否を分ける最大のポイントです。営業で培った数字管理や事務での請求処理、人事での給与計算といった経験を“経理の言葉”に翻訳して伝えることで、未経験でも十分に戦えるのです。
大切なのは「受け身」ではなく「攻めの姿勢」。入社後すぐに基礎をキャッチアップし、数か月以内に業務改善や部門連携にも関わる姿勢を示せば、30代前半でも経理転職は成功できます。未経験から経理へ挑戦するなら、即戦力思考を持ち、自分の経験を正しく言語化することが最短ルートなのです。

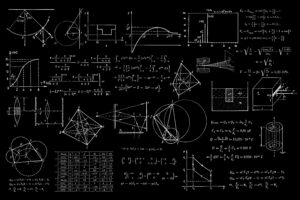







コメント