「FP&A(Financial Planning & Analysis)」という仕事に興味はあるけれど、自分に向いているのかどうか分からない――そんな不安を抱える人は少なくありません。
特に20代〜30代前半の就活生や第二新卒、未経験から年収アップを目指す転職希望者にとっては、「数字に強くないとダメ?」「経理や会計とは何が違うの?」といった疑問も多いはずです。
FP&Aは、企業の意思決定を数字で支える“経営の頭脳”とも言えるポジションです。分析力や論理的思考はもちろん、部門間の調整力やプレゼン力など、ビジネスの幅広いスキルが求められます。その一方で、すべてが専門知識で固められているわけではなく、未経験からでも段階的にステップアップすることが可能な職種でもあります。

めっちゃ魅力的な職種なので、
ぜひ具体的に考えてほしいで
この記事では、FP&Aという仕事の基本から、向いている人・向いていない人の特徴、未経験者が目指すために必要なスキル、キャリアステップや将来性まで、実践的な視点で詳しく解説します。自分に合うかどうかを見極め、納得感のあるキャリア選択につなげるためのヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。
FP&Aとは?|仕事内容と求められる役割の全体像
- FP&Aは「経営の意思決定」をサポートする役割
- データ分析や予算策定、業績モニタリングが主な業務
- 経理や財務とは異なり、「未来」に対する提案が中心
FP&A(Financial Planning & Analysis)は、財務数値をもとに経営判断をサポートするポジションです。主な仕事は、予算の策定、実績のモニタリング、予実差異の分析、そして将来の経営計画の立案支援など。「経営企画」とも重なる領域であり、数字を使って“ビジネスの羅針盤”となる役割を担います。
経理が「過去の数値を正しく記録する」ことに重きを置くのに対し、FP&Aは「未来を予測し、意思決定に活かす」ことに主軸があります。そのため、分析力や論理的思考に加え、経営層とのコミュニケーション力も必要不可欠です。部門横断的な調整も多く、社内でのハブ的な存在とも言えるでしょう。
またFP&Aの業務は、数字の単純な処理にとどまりません。売上の動向から人員計画まで、事業全体に関与するため、ビジネスモデルを理解し、数値の背景にあるストーリーを読み解く力が求められます。だからこそ、数字が読めるだけでなく、「なぜその数字になったのか」を考えられる人が活躍できる職種です。
FP&Aに向いている人の特徴とは?|思考力・行動スタイル・価値観から分析
- ロジカルに物事を考える力がある
- 数字を扱うことに抵抗がなく、分析が好き
- 事業部門・経営陣・財務経理など多様な立場と丁寧にやり取りできる
- 自ら情報を取りに行く主体性がある
- 「正解のない問い」に対して仮説を立てて動ける
- 自分の分析が意思決定に役立つことにやりがいを感じられる
FP&Aの仕事は、数字を通じて経営と現場をつなぐ「翻訳者」的な役割を担います。たとえば、経営陣が描くビジョンを数字に落とし込み、予算として設定したり、逆に現場で起きている売上の変化やコスト構造の変化を、財務視点でレポートして経営にフィードバックしたりします。このように、ただ数字を見て終わりではなく、その背景を読み解き、伝わるように説明・提案する力が求められます。
1. ロジカルに物事を考える力がある
FP&A業務では「ロジカルシンキング」が不可欠です。数字の増減を見て、「何が起きたのか」「なぜそうなったのか」といった因果関係を仮説として立て、必要なデータを収集し検証する力が求められます。そのうえで、経営層や現場に対して改善策を提示していく必要があります。ただの報告で終わらず、“分析を通じて価値を生む”ことがFP&Aの本質です。
2. 数字を扱うことに抵抗がなく、分析を楽しめる
FP&Aは日々の業務で数字と向き合います。予実差異、KPI、コスト構造など、多くのデータを扱いながら、ビジネス全体を数値的に把握することが求められます。単に電卓を叩くのではなく、数字の意味を読み取り、背後にあるストーリーを解釈できる人に向いています。
3. 多様な部門と丁寧にやり取りできるコミュニケーション力がある
FP&Aは経理や財務などのバックオフィス部門だけでなく、営業・マーケティング・製造といった事業部門とも頻繁に連携します。たとえば、売上の変化を分析するには現場の状況を把握する必要があるため、現場社員との信頼関係が不可欠です。立場や視点の異なる人たちと丁寧に対話し、納得感を持ってもらう力が求められます。
4. 自ら情報を取りに行く「主体性」がある
FP&Aの仕事は、上から指示されるばかりではありません。むしろ、「今この状況で、何を分析すべきか」を自分で考え、必要な情報を集めることが多くあります。分析テーマを設定し、関係者にヒアリングをかけてデータを整え、自ら課題解決に動ける人が成果を出せる仕事です。
5. 「正解のない問い」に対して仮説を立てて進められる柔軟性
FP&Aの業務にはマニュアル通りの正解は存在しません。環境や前提条件が日々変わるなかで、「現時点での最適解」を仮説ベースで導き出す力が重要になります。完璧なデータが揃わなくても、自分なりに仮説を立てて検証し、進めていける柔軟さがある人が向いています。
6. 分析を通じて経営に貢献することにやりがいを感じる
FP&Aは「経営に近いポジション」であり、数字の分析がそのまま意思決定や戦略に反映される重要な役割です。そのため、「自分の仕事が経営判断につながっている」という実感を持てる人ほど、モチベーション高く取り組める職種です。
FP&Aに向かない人の特徴とは?|ストレスの原因になりやすいポイント
- 明確な正解や手順がない業務にストレスを感じやすい
- 他部門との調整や交渉を避けたい人には不向き
- 数字を見ることに苦手意識があると業務が重荷になる
- マルチタスクや変化に弱いと対応が難しい
向いている人がいる一方で、FP&Aの業務にストレスを感じやすいタイプも存在します。ここでは「どんな特性の人がFP&Aに不向きか」、よくあるケースを具体的に整理してみましょう。転職や配属前に、自分の性格や価値観と照らし合わせておくことが重要です。
1. 明確な正解や手順がない業務にストレスを感じやすい人
FP&Aの仕事は、常に「正解のない問い」と向き合う連続です。経営環境は変化し続けるため、手順通りに作業すれば終わる仕事ではなく、自分で判断し、仮説を立てて進める力が求められます。そのため、「明確な指示が欲しい」「正解がないと不安」というタイプには、負担が大きく感じられるかもしれません。
2. 人とのやり取りや調整業務が苦手な人
FP&Aは社内のさまざまな部署と連携しながら動きます。事業部門から情報を引き出し、経営層に説明し、財務や経理とすり合わせるなど、立場の異なる人たちとの橋渡しが日常的に発生します。このような対話や調整を面倒に感じる人、他人と関わる業務を避けたい人には適性が低い可能性があります。
3. 数字に苦手意識がある人
FP&Aの基盤は「数字」です。売上や利益、原価やKPIなど、あらゆる情報を数字で分析・判断するため、数値に対する抵抗感があると業務の多くがストレスになってしまいます。また、数字の背景を読み解く思考力も求められるため、表面的な数値処理で終わらせてしまうタイプの人にも不向きです。
4. マルチタスクや変化への適応が苦手な人
FP&Aでは、複数のプロジェクトを同時に進めることが珍しくありません。加えて、経営戦略や業績の変化によって分析の優先順位が変わることもあり、臨機応変な対応力が求められます。常に同じ業務をコツコツとこなしたい人、変化の多さに疲れてしまう人には、継続的にストレスを感じる可能性があります。
実際にFP&Aに多いタイプ|私が働いてみてわかったこと
- 数字・会計・法務の基礎に強い
- 事業全体の流れを理解している
- 改善提案から推進まで一気通貫で関われる
私が実際にFP&Aとして働いて感じたのは、この職種で長く活躍している人には、いくつかの共通点があるということです。まず大前提として「数字に強い」のは必須条件ですが、それだけでは足りません。



数字を扱う部署として、
数字には徹底的に拘る、
そこは絶対に外せない
FP&Aは経理のように数字を“作る”だけでなく、その数字を分析し、経営判断や事業推進に活かす役割を担います。そのため、会計原則や財務三表の理解はもちろん、場合によっては契約やコンプライアンスに関わる法務的な知識も求められます。
特に強く感じるのは、「数字」「会計」「法務」の知識をベースにしつつ、事業理解が深い人ほど成果を出しやすいということです。例えば、予実差異を見つけても、その原因が市場環境の変化なのか、社内のオペレーション上の問題なのかを切り分けるには、事業モデルや業務プロセスを理解している必要があります。そして、その背景を踏まえて経営層や事業部に改善策を提案し、実行まで推進できるのがFP&Aの価値です。
現場で目立っていたのは、「数字から課題を抽出 → 改善の仮説を立案 → 関係者を巻き込んで実行」という一連の流れを自走できる人でした。逆に、分析だけで終わり、改善提案や推進ができないと「経営判断に活かせる数字」にはなりません。FP&Aは、分析屋とプロジェクト推進者のハイブリッドのような存在だと実感しています。
また、活躍している人の多くは、ExcelやBIツールを使いこなす“手元のスキル”と、経営会議でも通用する“説明力”を兼ね備えています。経営層にとっては数字の正確性以上に、「その数字が何を意味するのか」「どう動くべきか」というストーリーが重要だからです。このストーリー作りには、法務・会計の知識や事業理解が自然に織り込まれます。
未経験からFP&Aを目指すために必要なスキルセット
- Excel・PowerPointなどの基本的なPCスキルは必須
- 会計や財務三表の理解があると実務での吸収が早い
- 論理的思考力とビジネスの構造を掴む力が求められる
- データ分析・資料作成・プレゼン経験があると有利
FP&Aは高度な専門職に見えますが、実は汎用的なスキルを組み合わせて挑戦できる職種でもあります。未経験から目指す場合、まずはExcelを使った表計算や関数の操作、PowerPointでの資料作成など、基本的なPCスキルをしっかり押さえておくことが第一歩です。
次に重要なのは、財務三表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書)の基礎理解です。経理経験がなくても、オンライン講座や書籍などで数値のつながりや構造を学ぶことで、FP&A業務に必要な土台が身につきます。簿記2級レベルの知識があると、実務への理解が格段に進みます。
さらに、FP&Aでは「数字から意味を読み取る力」や「問題を構造的に捉える思考力」が重要です。たとえば営業やマーケティングの経験者でも、KPI管理や予算管理を担当した経験があれば、そのスキルを応用することができます。実際の業務では、数字を分析し、スライドに落とし込み、相手に伝える力が求められるため、仮説思考やプレゼン能力も武器になります。未経験でも、近い領域での経験を言語化できれば、十分に採用対象となるでしょう。
向き不向きはどう見極める?|自己分析・現場経験のポイント
- 自己分析では「考え方の癖」や「価値観」に注目する
- 業務体験を通じてリアルな温度感を知るのが有効
- 副業・異動・インターンなどで“お試し経験”も可能
FP&Aに向いているかどうかを見極めるには、まず「自分がどう考えるタイプか」「どんな価値観を大事にしているか」を自己分析することが有効です。たとえば、「不確実な状況でも自分で判断して動くことが苦にならないか」「数字で物事を考えるのが好きか」といった視点で、自分の思考パターンを棚卸ししてみましょう。
加えて、実際の業務を経験してみることが最も確実な方法です。たとえば経理や事業企画の仕事を一部でも担当できれば、数字を扱う感覚や、他部門とのやり取りがどのようなものかをリアルに体験できます。配属や異動を希望してみるのもひとつの手段ですし、職種体験型の副業や業務委託案件にチャレンジするのも現実的なアプローチです。
さらに、未経験者向けのインターンや職場見学会などを活用すれば、実際に働く人の話を聞くこともできます。やってみて「楽しい」「工夫のしがいがある」と感じられるかどうかが、適性を測る大きなヒントになります。最初から完璧に判断しようとせず、まずは“近づいてみる”ことが、向き不向きを見極めるための第一歩です。
FP&Aに向いているか不安な人におすすめのキャリアステップ
- 経理や営業企画など、隣接職種を経由するステップが現実的
- 業務の一部から「数字を扱う経験」を積むのが第一歩
- 転職前にスキルや適性を“試せる環境”を探すことが大切
FP&Aに興味はあるけれど、「自分に本当に向いているのか分からない」という人は少なくありません。そんなときはいきなりFP&Aを目指すのではなく、経理・営業企画・事業企画といった隣接職種からステップを踏むのが効果的です。特に経理で財務三表に触れたり、営業企画でKPIを管理する経験は、FP&Aに通じるスキルになります。
まずは「数字を見る」「仮説を立てて検証する」といった業務に少しでも関われる環境に身を置いてみましょう。たとえば、営業職で売上データの集計を担当する、管理部門で予算の進捗管理を任される、といった実務を通じてFP&A的な要素を試すことができます。
また、現職での異動希望や社内公募、副業・業務委託でのプロジェクト参加など、段階的に経験を積めるルートもあります。特に未経験からいきなりFP&Aの中途採用を狙うのはハードルが高いため、まずは「近い領域に触れてみる」ことが成功への鍵となります。向いているか不安な人ほど、段階的に経験を積むキャリア設計が安心です。
向き不向きに左右されない!キャリアとしてのFP&Aの魅力と可能性
- 経営に近い立場で“意思決定”に関われるやりがいがある
- ビジネス全体を俯瞰できるスキルが身につき、汎用性が高い
- 市場価値が高く、将来的なキャリアの選択肢が広がる
FP&Aは、数字を通じて経営に関わることができる数少ないポジションの一つです。事業戦略や投資判断などに対して自らの分析や提案が影響を与えるため、実務を通じて「会社を動かす感覚」が味わえる点が大きな魅力です。現場と経営の間に立つポジションだからこそ、調整力や視座の高さも自然と鍛えられます。
また、FP&Aは特定の業界や企業に依存しにくく、どのビジネスでも必要とされる機能です。財務分析や予算管理、KPI設計といったスキルは、経営企画や事業責任者、スタートアップCFOといった多彩なキャリアにもつながります。いわば「ビジネスの共通言語」を習得できる職種と言えるでしょう。
さらに、実務経験を通じて得られるのは“数字を扱える力”だけではありません。ビジネスモデルを理解する力、変化に対応する思考、成果をわかりやすく伝える力など、どの職種でも活かせるスキルが多く身につきます。たとえ最初は向いていないと感じても、続ける中で大きな武器になる知見を得られる。それが、FP&Aというキャリアの強みです。
まとめ
FP&Aは、経営に深く関わる“数字を扱うプロフェッショナル”として、論理的思考力や分析力、部門間の調整力など、さまざまなスキルが求められる職種です。向いている人の特徴としては、ロジカルに考える力、数字への抵抗感のなさ、自律的に動ける姿勢が挙げられます。一方で、明確な正解やルールがないことに不安を感じる人や、コミュニケーションが苦手な人にはストレスの多い職種とも言えるでしょう。
とはいえ、向き不向きだけでキャリアの可能性を狭める必要はありません。経理や営業企画など、隣接領域でスキルを磨きながらFP&Aの素地を身につけることも十分に可能です。数字を読む力やビジネスを俯瞰する視点は、どのキャリアにも応用が利く“汎用性の高い武器”になります。
「なんとなく興味はあるけど、自信がない」と感じている方こそ、まずは自己分析や部分的な業務経験から、少しずつFP&Aに近づいてみることをおすすめします。キャリアの選択肢を広げる一歩として、FP&Aは非常に魅力的なフィールドです。

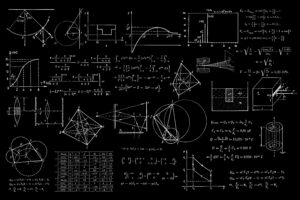







コメント