皆さん、転職の時って求人情報の年収や会社規模だけで選んでいませんか?
財務経理・FP&A・経営企画といったコーポレート系の職種は、企業の成長を裏側から支える重要な役割を担っています。しかし、転職市場に出ている求人をよく見てみると、同じ肩書きであっても実際の仕事内容や期待されるスキルは企業によって大きく異なります。そのため「思っていた業務と違った」「専門性を磨けないまま時間だけが過ぎてしまった」といったミスマッチが起こりやすいのが現実です。

どんなリスクがあるのか、
を事前に理解するのが超大切
特にベンチャーや中小企業では、経営層が営業畑出身ばかりでコーポレート部門への理解が乏しいケースも少なくありません。その結果、重要な判断や分析に関与できず、単なる作業担当に終始してしまう危険性があります。また、求人票では「経営企画」や「FP&A」と書かれていても、実態は資料作成や雑務中心だったり、「システム導入プロジェクトまで対応」といった想定外の業務が紛れている場合もあります。
だからこそ転職活動では、求人票の言葉だけを鵜呑みにするのではなく、経営層のスタンスや業務範囲、入社後のキャリアパスまでを冷静に見極めることが欠かせません。さらに、面接の場で具体的な質問を投げかけたり、転職エージェントやOB訪問を通じて裏情報を得たりすることも、ミスマッチを防ぐ有効な方法です。
本記事では、実際に転職を経験した立場から「財務経理・FP&A・経営企画で注意すべき点」を整理しました。これから転職を考える方が、自分に合った環境を選び、キャリアを確実に前進させるための参考になれば幸いです。
経営層のコーポレート部署の理解度を見極める
- ベンチャーや中小規模では経営層が営業畑出身ばかりで、コーポレートを軽視するケースがある
- 評価者がコーポレートの重要性を理解しているかどうかがキャリア形成に直結する
- 数字管理や内部統制への意識が薄い環境では、成長機会よりも雑務に追われやすい
転職先を検討する際に、まず注目すべきは「経営層がコーポレート部門をどれだけ理解しているか」です。これは本当に重要です。
特にベンチャーや中小企業では、役員陣が営業や事業開発出身者で占められていることが少なくありません。その場合、コーポレート部門は「事業を支えるための後方支援」に過ぎないと認識され、評価やリソース配分が後回しにされがちです。



小規模の会社って本当に社長が全て
実際にその意識を変えることは本当に難しい、、
コーポレート業務は会社の基盤を支える重要な機能です。財務経理は資金繰りと決算を安定させ、FP&Aは経営判断を数字で支え、経営企画は戦略を形にします。にもかかわらず経営層がその役割を理解していなければ、単なる「管理コスト」と見なされてしまい、成果が正当に評価されにくい状況に陥ります。
評価者がコーポレートの重要性を理解していない
さらに問題なのは、評価者である役員が「コーポレートに何を期待するか」を言語化できていないケースです。営業出身のトップほど「売上を伸ばすことが最優先」という発想に偏り、内部統制や業務プロセス改善への投資を軽視しがちです。その結果、経理担当者は毎月のルーチン業務に追われ続け、FP&Aは戦略的な分析よりも資料作成係に押し込められるリスクが高まります。
こうした環境では、専門スキルを磨く機会が得られないまま年数だけが経ってしまいます。転職者にとってこれは大きな痛手であり、次のキャリアに繋がる実績が積み上がらない危険性をはらんでいます。逆に、経営層がコーポレートの価値を理解している会社では、財務経理は経営管理のパートナーとして認められ、FP&Aや経営企画は戦略の中枢に組み込まれる可能性が高まります。
会社の見極め方
その見極め方としては、面接や面談の場で「経営層が数字や管理にどんなスタンスを持っているか」を確かめることが効果的です。例えば、「経営陣がどのくらい会計や財務に関与しているか」「経営会議でどのように数字が議論されるか」といった質問を通じて、コーポレートを単なるサポートではなくパートナーとして捉えているかを探ることができます。
また、求人票や面接で「管理部門は少人数で幅広い業務を任される」と強調されている場合は注意が必要です。一見やりがいがありそうに見えても、実態は人手不足による業務過多であり、経営層が十分に理解しないままコーポレートを“便利屋”扱いしている可能性が高いからです。



後は、
財務経理等の現場系のキャリアを経てCFOや部長になっている人がいるかどうか、ていう点も重要やで
最終的に、転職者にとって重要なのは「誰が自分を評価するか」「その人がコーポレートをどう位置付けているか」です。経営層に理解があれば、少数精鋭の環境でもやりがいを持って働け、成果が評価され、キャリア形成につながります。逆に理解が乏しい場合は、労力ばかりかかり、評価も得られず、成長実感も得にくいでしょう。
つまり、転職の成否は待遇や仕事内容だけではなく、経営層のコーポレート観に大きく左右されます。役員が数字や管理の重要性を理解している会社を選ぶことこそ、財務経理・FP&A・経営企画のキャリアを築く上での第一歩なのです。
よくあるケース(実際にあったイケイケベンチャー企業の場合)
大企業の場合はあまり見られませんが、ベンチャーや中小企業では「まずは売上を伸ばすこと」が最優先で、会社全体が営業ドリブンで動いているケースが多くあります。利益や内部管理よりも「スピードとトップライン」が重視されるため、コーポレート部門は軽視されやすいのが現実です。
さらに、ベンチャー企業では社長や役員の影響力が非常に大きいのが特徴です。その役員が営業畑や事業開発出身でコーポレートへの理解が乏しい場合、財務経理・FP&A・経営企画の立場は非常に不安定になります。意思決定の場に呼ばれないどころか、成果そのものが正しく評価されないという状況に陥りがちです。
コーポレートの業務は「できて当たり前」とみなされることが少なくありません。例えば財務経理で決算を締めても、FP&Aで予算分析を仕上げても、「当たり前でしょ」と一言で片付けられてしまう。経営企画が中期戦略の提案をしても、短期的な売上至上主義に押し流され、結局は資料作成係に追いやられることもあります。
しかし、会社が上場を視野に入れる段階になれば、外部からも内部からも「適切なフロー設計」や「正確な数字管理」が必須になります。財務経理は決算や開示の正確性を担保し、FP&Aは投資家や経営層に対して数字を裏付けにしたストーリーを提示する役割が求められます。経営企画も、成長戦略を描くだけでなく、内部統制を踏まえた計画立案にシフトしていく必要があります。
このとき問題になるのが、「その努力を経営層が本当に理解してくれるのか」という点です。短期的に売上ばかりを見てきた経営陣にとって、コーポレートの地道な整備や分析は成果と認識されにくいのです。その結果、経理は「ただ数字をまとめる人」、FP&Aは「資料を作る人」、経営企画は「役員の意向を文書化する人」という低い評価に留まるリスクがあります。
つまり、イケイケのベンチャーほど「表面的には華やかだが、実際はコーポレートへの理解が薄い」というギャップが起きやすいのです。転職する際には、この構造を理解した上で、経営層がコーポレートの重要性を認め、適切に評価する土壌があるかどうかを慎重に見極める必要があります。
業務範囲は“作業”だけか、意思決定権を求められているかを確認する
- 財務経理・FP&A・経営企画は「作業担当」か「意思決定に関与する立場」かでキャリアの質が大きく変わる
- 決算や会計処理の判断、分析・提言の余地があるかどうかを事前に見極めることが重要
- 「経営企画」と名乗っていても資料作成や雑務に偏るケースが多い
- 「なんでも屋」求人は戦略業務か単なる延長線上の業務かを確認する必要がある
転職活動において、求人票や募集要項には「経理」「FP&A」「経営企画」といった職種名が並びます。しかし、同じ職種名であっても、実際に求められる役割は会社ごとに大きく異なります。
特に注意すべきなのは、業務範囲が単なる“作業担当”で終わるのか、それとも“意思決定に関与する役割”を担えるのかという点です。ここを見極めずに入社してしまうと、キャリアに大きな差がついてしまいます。



自身が望む業務内容かどうか確認しような
財務経理:仕訳入力要員になってしまわないか
財務経理の募集でも、「伝票入力や月次決算補助」といったルーチン業務が中心の場合と、「会計処理の判断や監査対応」といった意思決定要素を含む場合があります。前者では経験を積んでもスキルの幅が広がらず、後者に比べて市場価値の向上は限定的です。
一方で、会計処理の是非を判断する立場や、新しい会計基準への対応をリードする経験があればよりレベルの高いキャリアが築けます。つまり「経理経験」とひとくくりにしても、将来的に評価される人材になるかどうかは、業務範囲の質によって決まるのです。
FP&A:数字を集計するだけの人になってしまわないか
FP&Aの求人では、「予算策定」「差異分析」といった言葉が並びますが、実際には「数字を集計し、資料を作るだけ」というポジションも多く存在します。エクセルで集計し、グラフを作って会議資料を提出するだけでは、経営のパートナーとしての経験は積めません。
本来のFP&Aの役割は、データを読み解き、事業の課題や改善余地を見つけ、経営に提言することです。もし業務範囲が「分析・報告」まで任され、経営会議に参加して議論できる環境なら、意思決定に直結するキャリアが積めます。逆に「集計担当」に留まるなら、FP&Aの名を冠していてもただの作業者でしかありません。
経営企画:資料作成係になってしまわないか
経営企画も同様に、求人票では「戦略立案」「経営支援」といった華やかな言葉が並びます。しかし、実態は「取締役会や投資家向け資料の作成」「数値管理表の更新」といった作業中心のケースが少なくありません。
もちろん資料作成も大事ですが、それだけに終始してしまえばキャリアの幅は広がりません。経営企画として本当に戦略に関与できる環境なのか、それとも経営陣の指示をただ形にするだけなのかを見極める必要があります。ここを誤ると、「経営企画経験者」と名乗っても、市場では“作業担当”としてしか評価されないリスクがあるのです。
「なんでも屋」求人の裏に潜む落とし穴
特に注意したいのは、ベンチャー等である「幅広くコーポレート全般を担当」といった求人です。一見やりがいがありそうに見えますが、実態は人手不足を補うための“便利屋”ポジションである場合が多いです。
戦略的な業務を任せてもらえるなら良いですが、経理・総務・法務・人事と何でもやらされ、結局は専門性が身につかないまま数年が過ぎてしまうことも少なくありません。転職市場で高く評価されるのは「幅広く何でもできる人」ではなく、「専門領域で意思決定に関与できた人」です。
面接で確認すべきポイント
実際に業務範囲を見極めるためには、面接での質問が重要です。例えば、
- 「決算や会計処理の判断は誰が行っていますか?」
- 「FP&Aの提言は経営会議でどのように扱われていますか?」
- 「経営企画が戦略立案にどの程度関わっていますか?」
こうした質問をすることで、会社があなたに「作業担当」を求めているのか「意思決定支援」を求めているのかが浮き彫りになります。
キャリアを左右する“業務範囲”の見極め
結局のところ、転職で得られる経験は「業務範囲の質」に依存します。作業中心の環境では年数を重ねてもスキルが伸びず、次の転職で評価されにくくなります。一方、判断や提言の経験を積める環境であれば、短期間でも大きなキャリア価値を得られます。
そのため求人票の肩書や仕事内容の表面的な表現に惑わされず、具体的に「自分は意思決定にどう関わるのか」を確認することが不可欠です。
入社後のキャリアパスを想定できるか
- 入社時点でどんなキャリアの広がりがあるかを確認することが重要
- “便利屋ポジション”に留まると専門性が磨かれず、次の転職で不利になる
- 面接や求人票で「数年後の役割」「評価の軸」を確認することがミスマッチ回避につながる
転職活動では「入社後すぐの仕事内容」に目が行きがちですが、実際に重要なのは「数年後にどんなキャリアが描けるか」です。求人票に魅力的な業務内容が並んでいても、将来的に専門性を積み上げられない環境では、キャリア形成に大きな影響が出ます。
例えば財務経理であれば、最初は仕訳や月次決算が中心でも、数年後に連結決算や開示、税務戦略まで任される道筋があるのかが重要です。単なるルーチン業務に留まる環境では、市場で評価されるスキルが積みにくくなります。
FP&Aの場合も同様です。最初は予算集計や資料作成でも、いずれは経営会議での分析報告や、事業戦略に基づく提言へと役割を広げられるかどうかでキャリアの価値が変わります。意思決定に関わる経験が積めれば、市場価値は格段に高まります。
経営企画においては、役員会用の資料作成に終始するのか、それとも中期経営計画や新規事業戦略に関わるのかが将来性を左右します。戦略立案の経験が積めるかどうかで、次のキャリアの選択肢は大きく変わってきます。
注意すべきは、入社直後は“何でも屋”のように幅広い業務を求められる会社です。広く経験できるように見えても、実態は人手不足の穴埋めであり、専門性が身につかないまま数年を過ごしてしまうリスクがあります。そのため、面接時には「3年後・5年後に期待される役割」「昇進や異動の実績」「評価の基準」などを具体的に確認することが欠かせません。入社後のキャリアパスを想定できるかどうかが、転職を成功させる鍵になります。
面接で確認すべき具体的な質問
- 役割分担の明確さを確認し、雑務に偏らないか見極める
- 上長や経営層のバックグラウンドを把握し、評価基準を推測する
- 経営会議や戦略議論にどの程度関われるかを質問する
- 過去の異動・昇進事例を確認し、キャリアパスをイメージする
転職で最も難しいのは、求人票だけでは「実際の業務内容」や「働く環境」が分からないことです。そのため、面接では待遇面以上に、仕事の中身や成長機会を具体的に見極める質問をすることが欠かせません。
まず確認すべきは役割分担の明確さです。「経理と経営企画の両方に関わる」と書かれていても、実態は経理のルーチンが中心ということもあります。面接では「日々の業務割合」や「定常業務と企画業務のバランス」を具体的に聞くと、求人票の抽象的な表現の裏を読み解けます。
次に重要なのが上長や経営層のバックグラウンドです。営業畑出身の役員ばかりなら、コーポレートの評価が軽視される可能性もあります。面接で「上長の経歴」や「経営層が数字をどう扱っているか」を聞くことで、意思決定にどれだけ関われる環境かを判断できます。
さらに、経営会議や戦略議論への関与度も確認しましょう。「分析結果や提案はどの場で使われますか?」「経営会議に参加できますか?」と尋ねることで、資料作成係で終わるのか、意思決定の現場に踏み込めるのかを見極められます。
最後に、キャリアパスの事例を押さえることも重要です。「過去に同じポジションの人はどんなキャリアを歩んでいますか?」と聞けば、その会社での成長の可能性を具体的にイメージできます。
つまり、面接は待遇を確認する場ではなく、「この会社で本当に成長できるか」を見極める場です。役割分担・上長の背景・会議参加の有無・キャリア事例を掘り下げる質問を通じて、入社後のミスマッチを最小限に抑えることができます。
まとめ
転職活動において、求人票に書かれている職種名や表面的な業務内容だけで判断するのは危険です。財務経理・FP&A・経営企画といった肩書きが同じでも、会社ごとに役割や期待値は大きく異なり、入社後のキャリアの質を左右します。
特に注意すべきは「経営層のコーポレート理解度」「業務範囲の実態」「求人の背景(常に募集していないか)」です。これらを見極めずに入社すると、便利屋ポジションや単なる作業担当に陥り、専門性を磨けないまま数年を過ごしてしまうリスクがあります。
一方で、会計処理の判断や経営会議への参画、戦略立案などに関われる環境に身を置けば、短期間でも大きな成長機会を得られます。つまり、転職の成否は待遇や肩書きよりも「どこまで意思決定や判断に関わる経験が積めるか」にかかっています。
そのためには、面接で「上長や経営陣のバックグラウンド」「実際の役割分担」「過去のキャリアパス事例」を具体的に確認し、求人票では分からない“実態”を掴むことが不可欠です。さらに転職エージェントやOB訪問を活用して裏情報を得ることも、ミスマッチを防ぐ有効な手段となります。
転職はキャリアの大きな分岐点です。目先の条件にとらわれず、自分のスキルを活かし伸ばせる環境かどうかを冷静に見極めることが、財務経理・FP&A・経営企画職で長期的に成功するための最も確実なステップだといえるでしょう。

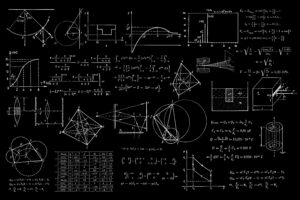







コメント