「経営企画ってなんだかかっこいい」「会社の頭脳として戦略を動かせる花形部署だ」──そんなイメージを持つ人は多いでしょう。
しかし現実には、「経営企画はつらい」「やめとけ」「思ったよりつまらない」といった声も少なくありません。
なぜ、華やかに見える仕事がここまでネガティブに語られてしまうのか。そこには、激務や成果責任の重さ、経営陣と現場の板挟み、戦略よりも数字管理に追われる日常といった厳しい現実があります。

経営企画って幅広い、
疲弊してる人とめちゃ輝いている人に2分化してる
とはいえ、経営企画は単に「しんどい仕事」で終わるわけではありません。優秀な人材が集まり、多様なバックグラウンドを持つメンバーと働くことで、自分の成長やキャリアの可能性を大きく広げられる場でもあります。
本記事では、経営企画が「つらい」「やめとけ」と言われる理由を整理しつつ、私が実際に経営企画として働いた経験から、実際に働く人たちのリアルな状況やキャリアの魅力までを解説します。
これから経営企画を目指す方や、異動・転職を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
経営企画は本当につらい?「やめとけ」と言われる理由
- 激務で成果責任が大きくプレッシャーが強い
- 経営陣と現場の板挟みになりやすい
- 戦略立案より作業中心になることも多く、期待とのギャップが大きい
経営企画は「会社の頭脳」とも言われる重要な部門ですが、同時に「つらい」「やめとけ」と評されることも少なくありません。華やかなイメージとは裏腹に、実際の現場ではプレッシャーや矛盾に苦しむ場面が多いからです。
強烈なプレッシャーと過酷な働き方
経営企画が「つらい」と言われる大きな理由のひとつが、激務と成果責任の重さです。経営陣からは短期間での資料準備や数字分析を求められ、取締役会や経営会議の日程に合わせて深夜残業や休日対応を強いられることも珍しくありません。
さらに、提示する数字やシミュレーションが経営判断に直結するため、誤りは許されません。経営層からは「数字で語れ」「根拠を示せ」と厳しく詰められることもあり、その緊張感は他部署よりも格段に大きいのです。こうしたプレッシャーは、キャリアを積む上で貴重な経験になる一方で、「しんどい」「続けられない」と感じる原因にもなります。
板挟みと期待とのギャップ
もうひとつの大きな要因が「板挟み構造」と「期待ギャップ」です。経営陣の方針を現場に落とし込むと「現実を分かっていない」と反発を受け、逆に現場の声を上に伝えると「数字で裏付けろ」と詰められる。この調整役として常に矢面に立つのが経営企画です。
また、入社前に思い描いていた「戦略立案の最前線」というイメージとは異なり、実際には予算管理や数値集計といった作業が中心になることも多いです。やりがいを求めて飛び込んだ人ほど、このギャップに苦しみ、「やめとけ」と言いたくなる瞬間が訪れます。
単なる作業者に落ちると経営企画がつまらなくなるワケ
- 経営会議用の資料作成や数字集計ばかりになると「作業者化」する
- 戦略立案や意思決定支援のやりがいを感じにくい
- 本来の成長機会を逃し、キャリア価値が限定的になる
経営企画というと「会社の頭脳として戦略を動かす花形部門」というイメージを持つ人も多いでしょう。しかし実際に働いてみると、数字をまとめて報告するだけの“作業者”になってしまい、「思っていた仕事と違う」と失望するケースが少なくありません。
作業に偏ると「経営の頭脳」から遠ざかる
経営企画は本来、会社全体の方向性を描き、経営判断をサポートする役割を担います。
しかし実際には、経営会議や役員会に向けた資料作成、数字の更新などに追われ、「作業者」として扱われてしまうことが少なくありません。
この状態が続くと、自分が経営に関わっている実感を得にくくなり、「ただのデータ入力係」としての虚しさを感じてしまいます。本来期待していた「戦略立案」や「意思決定への影響力」とのギャップが、仕事をつまらなく感じさせる大きな要因になります。
成長機会を逃すとキャリアも限定される
もう一つの問題は、作業に終始するとスキルが磨かれず、成長の機会を逃してしまうことです。
数字の集計や資料更新ばかりでは、分析力や提案力は身につかず、転職市場でもアピールできる経験が限定的になります。
経営企画の醍醐味は、課題を見つけて改善策を提案し、全社を巻き込む経験にあります。しかし「作業者化」してしまうと、そのような場面に参加できず、結果的に「経営企画にいる意味がない」とすら感じてしまうのです。
つまり、経営企画が「つまらない」と言われる背景には、作業に埋もれて役割の本質を果たせない構造的な問題が潜んでいます。やりがいを得るためには、自ら積極的に提案や改善に踏み込み、「経営の頭脳」としての役割を取り戻すことが不可欠です。
実際によくいるつまらなさそうな人
実際に経営企画の現場には、「つまらなさそうに働いている人」が一定数います。彼らに共通しているのは、与えられた作業だけをこなし、自分の専門性や高度なスキルを発揮できていない点です。たとえば、経営会議用の数字更新やパワーポイントの修正といった単純作業に埋もれてしまい、本来期待される戦略的な提案や課題発見に進めていないのです。
もちろん、作業そのものは経営企画の基盤です。数値や資料を理解し、自分でもきちんと回せることは欠かせません。しかし重要なのは、そこから“次のプロセス”へ移行できるかどうかです。単なる報告で終わらせずに、データの裏に潜む課題を抽出し、自分の言葉で戦略として発信できるかどうか。さらに一歩進めて、その分析を仕組み化し、現場に落とし込んで自走できるように整えることが求められます。
逆に言えば、自らの発信力や確固たる専門性を持っていない人は、この次のプロセスに到達できません。その結果、作業に終始してしまい、やりがいを感じられず「経営企画はつまらない」と周囲から見られる存在になってしまいます。



少しずつでも与えられた業務+αで価値を出していく、
それが出来るかどうかで面白さが変わる
つまり、“作業から戦略へ”と進めるかどうかが、経営企画として輝けるか、それとも単なる作業者で終わってしまうかの分かれ道なのです。
経営陣と現場の板挟みになる「しんどさ」
- 経営陣からは「数字で語れ」「すぐに成果を」と強いプレッシャーを受ける
- 現場からは「実現不可能だ」「現実を分かっていない」と反発を受ける
- 板挟みの立場で調整を担うため、精神的なストレスが大きい
経営企画の大きな特徴のひとつが「経営陣と現場をつなぐ役割」です。しかしそれは同時に、双方の板挟みになる“しんどさ”を抱えることを意味します。トップからは厳しい要求を受け、現場からは不満や抵抗を受ける。その矢面に立つのが経営企画なのです。
経営陣からのプレッシャーは数字とスピード
経営陣が経営企画に求めるのは、「意思決定を支えるための明確な数字」と「短期間での成果」です。会議に向けては詳細なデータを求められ、時には「数字で語れ」と詰められることもあります。準備期間が短くても、経営層の日程は絶対であり、深夜残業や休日出勤をしてでも間に合わせる必要があるのです。
さらに、経営陣は戦略的な提案に対しても「根拠となるシミュレーションは?」「リスクはどう管理する?」と次々に問いかけてきます。これは当然重要なプロセスですが、受ける側からすれば強烈なプレッシャーであり、「つらい」と感じやすい瞬間です。
現場からの反発と摩擦
一方で、現場に経営の方針を落とし込むと、別の壁にぶつかります。
「そんな目標は到底無理だ」「現場の状況を分かっていない」と反発を受けることが多いのです。特に数値目標やコスト削減の施策を伝える際には、現場との摩擦が激しくなります。経営陣の意向を伝える立場として矢面に立つのは、常に経営企画です。
この時、ただ伝達するだけでは信頼を得られません。現場の声を吸い上げて経営陣にフィードバックし、両者の妥協点を探る調整力が求められます。しかし、どちらかに偏れば「経営側に寄りすぎている」「現場寄りで甘い」と批判される。まさに板挟みで消耗してしまうのです。
よくある板挟み事例①「高すぎる数値目標の設定」(経験談)
経営企画でよくある板挟みの一つが「高すぎる数値目標の押し付け」です。経営陣は株主や市場に向けて成長戦略を示す必要があり、「売上を前年比120%に」「営業利益率を数ポイント改善」といったトップダウンの指示を出すことがあります。
現場の声を拾うボトムアップではなく、あくまで経営判断として「とにかく頑張れ」というメッセージが下されることも珍しくありません。
一方、現場は市場環境や人員体制を理解しているため「現実的に達成は不可能だ」と反発します。営業や生産部門からは「これ以上はリソース的に限界」と厳しい声が上がるのです。その間に立つ経営企画は、経営陣の成長方針を尊重しつつも、根拠を数字で示しながら現実的な着地点を模索する役割を担います。経営層の期待と現場の実情をどうすり合わせるか、強いプレッシャーがかかる典型的な板挟み事例です。



大きな会社ほど、
役員や部長クラスの間に入るので本当に難しいタスク
よくある板挟み事例②「コスト削減施策の落とし込み」(経験談)
もう一つ典型的なのが「コスト削減施策」です。経営陣は利益改善のために「固定費を10%削減しろ」といった指示をトップダウンで出します。経営数字上は合理的に見えますが、現場からすれば「予算を削れば業務が回らない」「人員削減は士気が落ちる」と強い反発を招きます。とくに必要経費まで一律でカットするような方針は、実務担当者にとって死活問題です。
この板挟みの中で経営企画が担うのは、単なる伝達役ではなく「調整役」です。削減効果をシミュレーションし、代替案を提示したり、影響の少ない分野から段階的に導入する提案をするなど、両者の歩み寄りをつくる必要があります。経営陣の期待に応えつつ、現場の業務が止まらないように調整するのは非常に難しく、精神的な負荷も大きいのです。これもまた「経営企画はしんどい」と言われる典型例です。
数字管理ばかりで戦略に関われないジレンマ
- 経営企画の多くは予算管理やKPI集計に追われがち
- 戦略立案や提案に時間を割けず、やりがいを感じにくい
- データ整理だけでは「代替可能な人材」と見られてしまうリスク
経営企画というと「経営戦略を描く花形部門」というイメージを抱く人が多いでしょう。
しかし実際の現場では、予算の進捗管理やKPIの集計、会議資料の更新といった数字管理が業務の大半を占めるケースが少なくありません。
数字の正確性を担保することは当然重要です。経営陣が意思決定をするには信頼できるデータが不可欠だからです。
とはいえ、毎月の予算進捗や四半期ごとの着地見込みの確認に追われ続けると、「戦略を立てる余裕がない」というジレンマに陥ります。
本来期待されるのは、数字を整理したうえで「何が課題か」「どう改善できるか」を提案することです。
しかし、実務に追われると「数字を並べて報告するだけ」の存在になり、経営の意思決定に直接貢献できている実感が持てなくなります。
つまり、経営企画が「やりがいがない」「つまらない」と言われる背景には、戦略に踏み込めず、数字管理のループに縛られてしまう構造的な問題があるのです。経営企画として成長するためには、集めたデータをもとに自分なりの仮説を立て、改善提案や仕組み化に展開していく意識が欠かせません。
本来は優秀な人材が集まる経営企画という仕事
- 経営企画には事業部のトップ人材や外部コンサル出身者が多い
- 高度な分析力・戦略思考・コミュニケーション力が必須
- 成果を出せば経営層と近い立場でキャリアを広げられる
経営企画というと「つらい」「やめとけ」といった声もありますが、それだけで判断するのは早計です。
実際には、経営企画は会社の中でも特に優秀な人材が集まるポジションであり、成長とキャリアの可能性を広げられる舞台でもあります。
事業部やコンサル出身の精鋭が集まる
経営企画には、事業部で成果を出してきたエース級の人材が異動してくるケースが多く見られます。営業やマーケティングで数字を作ってきた人が、次のキャリアとして経営視点を磨くために配属されるのです。こうした人材は現場の事業理解が深く、経営との橋渡し役として強みを発揮します。
また、コンサルティングファーム出身者も数多く在籍しています。彼らは短期間でロジカルに課題を整理し、経営陣が納得する資料を仕上げる力に長けています。企業にとっては即戦力の戦略人材として重宝される存在です。つまり、経営企画は「優秀な人材の集まり」であり、部門全体の水準は高いのが実態です。
高度なスキルを活かしキャリアが広がる
経営企画で求められる能力は、数字を扱う分析力や論理的思考力にとどまりません。経営陣の意向を理解しつつ、現場の声をくみ取り調整するコミュニケーション能力やリーダーシップも不可欠です。経営層に近い立場であるため、成果を出せば直接的に信頼を得られるのも大きな特徴です。
その結果、経営企画で実績を積んだ人材は、将来的に事業責任者やCFO候補など、会社の中枢を担うキャリアパスを歩むケースも少なくありません。つまり経営企画は「つらい仕事」であると同時に、「優秀な人が成長と飛躍のチャンスをつかむ場所」でもあるのです。
経営企画のバックグラウンドは多様|事業部・コーポレート・コンサル出身
- 経営企画には事業部・コーポレート・コンサル出身など多彩な経歴の人材が集まる
- 各バックグラウンドが異なる強みを持ち、組織に多様性を生む
- キャリアの入口は広く、自分の経験を経営視点に昇華できる
経営企画というと「コンサル出身の人ばかり」と思われがちですが、実際は多様なバックグラウンドを持つ人材が集まっています。
事業部経験者やコーポレート部門の出身者、そして外部から転職してきたコンサルタントまで、それぞれ異なる強みを活かしながら経営に携わっているのです。
事業部・コーポレート出身者の強み
事業部から経営企画に異動してくる人は少なくありません。営業やマーケティングで実績を上げた人が、現場で培った知見を経営に生かそうとするケースです。現場感覚を理解しているため、経営陣の方針を落とし込む際にリアリティのある提案ができます。
また、経理や人事などのコーポレート部門から移ってくる人もいます。数字の正確性や制度面に強いため、経営管理や内部統制といった領域で力を発揮しやすいのが特徴です。こうしたバックグラウンドは、経営の安定運営に欠かせない存在と言えます。
コンサル出身者がもたらす視点
一方で、戦略コンサルティングファームから転職してくる人材も多いです。論理的思考力やデータ分析力に優れ、経営陣への提案資料を短期間でまとめ上げられる即戦力として期待されます。
ただし、コンサル出身者が強いのは戦略立案や分析の部分であり、現場の実行力や泥臭い調整に苦労する場合もあります。そこで事業部やコーポレート出身者との協働が生きてくるのです。異なる経歴の人材が互いに補完し合うことで、経営企画は多面的な価値を発揮できると言えるでしょう。
経営企画でキャリアを積むメリットと将来性
- 会社全体を俯瞰するスキルが身につき、幅広い経験を積める
- 経営層と近い距離で働くことで、意思決定プロセスを学べる
- 将来的にCFOや事業責任者など、経営に直結するキャリアパスが開ける
経営企画は激務や板挟みなどの大変さもありますが、それ以上に得られる成長やキャリアの将来性は大きな魅力です。
経営の中心に近いポジションだからこそ、他の部門では経験できない学びや人脈を得られるのです。
幅広いスキルと経営視点が身につく
経営企画では、予算策定や業績分析、事業戦略の立案、M&A検討など幅広い業務に関わります。これにより、財務・会計の知識からデータ分析、プレゼン力、プロジェクトマネジメントまで、多様なスキルを横断的に磨くことができます。
また、会社全体を俯瞰して見る経験が積めるため、自分の担当領域に閉じずに「経営視点」を身につけられるのも大きな強みです。この視座の高さは、どんなキャリアに進んでも必ず武器になります。
将来のキャリアパスが広がる
経営層と近い距離で働くことも大きなメリットです。経営陣の意思決定に日常的に触れることで、トップがどのように判断するのかを肌で学べます。その経験は他部署では得がたい貴重な資産です。
その結果、経営企画で成果を出した人材は、CFOや経営管理部長、事業責任者といった経営直結のポジションに抜擢されるケースも多くあります。また、転職市場でも「経営企画経験者」は高く評価され、コンサルやスタートアップのCxO候補などキャリアの選択肢が一気に広がります。
まとめ
経営企画は華やかなイメージとは裏腹に、激務・成果責任・板挟みのストレス・作業中心の現実といった要素が重なり、「つらい」「やめとけ」と言われる仕事です。
しかしその一方で、会社全体を俯瞰できる立場にあり、優秀な人材とともに成長できる大きなチャンスを秘めています。



どの会社でも花形
ポジティブにどんどんチャレンジすべき
重要なのは、現実の厳しさを理解したうえで、自分がどのように役割を果たせるかを考えることです。作業に終始せず、データから示唆を導き、戦略を提案・実行につなげられる人材になれば、経営企画は「しんどい」以上に「大きな成長をもたらす」キャリアになります。
つまり、経営企画は決して誰にでも向いているわけではありません。しかし本気で経営を学び、成長を望む人にとっては、これ以上ない経験を積める舞台なのです。

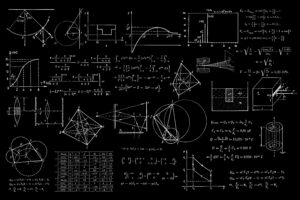







コメント